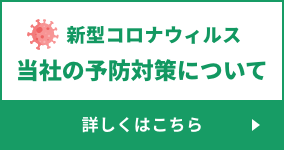沖縄の軍用地の歴史(後編) | 軍用地投資ブログ
2020年12月04日
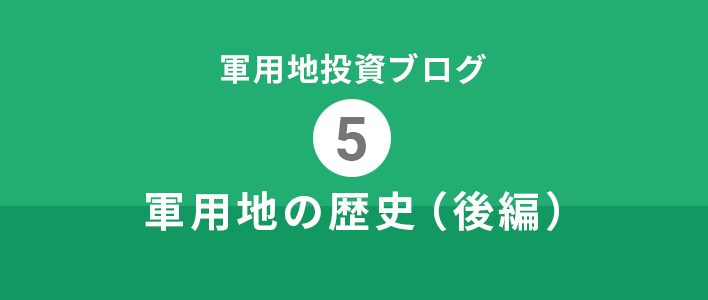
目次
土地連のはじまりと桑江朝幸
前回のブログでお話ししたとおり、米軍による基地用地の接収が常態化していくと、次第に軍用地料の正当な支払いを求める声が大きくなっていきました。こうした情勢のなか、立法院に集まった23の関係市町村代表によって、新たな民間組織として設立されたのが「市町村土地特別委員連合会(通称:土地連/現在の沖縄県軍用地等地主会連合会)」でした。
この項では、そんな土地連の初代会長に就任し、その後「ミスター軍用地」とまで呼ばれるようになった桑江朝幸氏(故人)について、少しふれてみたいと思います。
桑江朝幸氏について

土地問題解決のために渡米した桑江朝幸氏(右から2人目/沖縄県公文書館所蔵)。
桑江氏は、1918年に沖縄県の越来村(現:沖縄市)に生まれました。1938年に徴兵され、日中戦争以降アジア各国の戦地を転々としているなかで銃の暴発により左手に重傷を負い、日本本土に帰還。陸軍病院を退院後、近衛師団の板橋倉庫に勤めましたが、空襲により被害を受けると、残った物資を埼玉県へ疎開させるための仕事に従事しました。
それから間もなく、敗戦を迎えると部隊は解散。軍を離れた桑江氏は、浦和市(現:さいたま市)にあった復員局浦和支部に勤めることになりました。しかし、同年末には局内の人員整理の対象となり、紡績関連の会社に臨時職員として就職。その一方で、沖縄人同盟の活動に参加したり、沖縄出身の引揚者の対応などを精力的に行っていました。
その後、1946年12月に帰郷を果たした桑江氏を待ち構えていたのは、戦争と占領によって変わり果てた沖縄の姿でした。かつての風景からは想像できないほどの故郷の変貌ぶりに、桑江氏は失意のどん底に突き落とされました。
しかしながら、若かりし桑江氏はそんな厳しい状況に正面から向き合い、故郷の土地を取り戻すための方策を模索。越来村青年会を組織化するかたわら、沖縄民主同盟の結党にも参加するなど精力的に活動し、翌々年の1948年には越来村議会議員にも当選しました。
こうして少しずつ活躍の場を広げていった桑江氏は、軍用地住民部落代表者協議会を開催し、沖縄群島議会へ軍用地料支払いの陳述書を提出。自身も参考人として証言しました。また、1951年8月には地元紙の沖縄タイムスに自費で広告を出稿。軍用地料の支払いを米軍側に陳情するための署名の呼びかけや、軍用地主の代表者会議を実施するための告知を行い、人々の土地闘争を先導していきました。
こうした桑江氏の働きかけが実を結び、1953年6月には、軍用地問題の解決と軍用地主の財産権保護を目的とした「市町村土地特別委員連合会」が発足。活動の中心的役割を担っていた桑江氏が推薦され、初代会長の座についたのでした。
土地を守る「四原則」
さて、ここからは桑江氏の活躍とともに、土地闘争のその後の流れについてお話ししていきたいと思います。
桑江氏の奮闘もあり、借地料の正当な支払いを求める住民の声が大きくなると、米国民政府は「軍用地料の一括払い」方針を発表しました。
これは、地代(借地料の16.6年分とされた)を一括払いすることで永代借地権を得ようとするもので、長期間使用が予定される土地はすべて適用対象とされました。また米軍は、生活の場を失った人々を八重山諸島へ入植させ、一括払いされた地代をその原資に充てさせようともしました。
しかし、当然のことながら地主はこれに激しく反対。人々の請願を受けた立法院では「軍用地処理に関する請願決議」を全会一致で採択し、そのなかで「土地を守る四原則」を強く要請しました。
四原則の内容
一括払いの拒否
軍用地の買上げまたは永久使用、借地料の一括支払いは行わないこと。
適正な補償
住民の要求する適正な借地料を補償し、一年ごとの評価・支払いとすること。
損害の賠償
米軍による一切の損害について、住民の要求する適正賠償額を支払うこと。
新規接収の反対
米軍が使用していない土地は早急に開放し、新たな土地接収は行わないこと。
また、同決議の採択と同時に、行政府・立法院・市町村長会・土地連合会による四者協議会(後に市町村議会議長会が加わり五者協議会に)が組織され、連日のように米国民政府との折衝が行われるようになりました。
ところが、一定の権限しかもたない米国民政府と何度意見を交わしても具体的な解決策は得られないと感じた協議会は、各組織から代表者を選出し、使節団としてワシントンへ派遣することを決定。土地連の会長であった桑江氏も一員として加わり、アメリカ政府へ直談判に赴いたのです。
調査団の来訪とプライス勧告
前述のとおり、1955年5月に四者協議会の代表6人が渡米し、米下院軍事委員会にて「土地を守る四原則」を含むさまざまな問題についての話し合いが行われました。その結果、メルヴィン・プライス下院議員を委員長とする調査団(米下院軍事委員会軍用地調査団)が沖縄へ派遣されることに決定。同年10月には、現地沖縄でのリサーチが実施されることになりました。
こうしてアメリカ本国から正式な調査団が訪れたことで、住民たちは、何らかの解決策が提示されるものと大きな期待を寄せていました。ところが予想に反し、翌年6月に調査団が議会へ提出した報告書は、四原則を真っ向から拒絶するような厳しい内容のものでした。
「プライス勧告」と呼ばれるこの報告書には、沖縄における基地確保の重要性をはじめ、永代借地権の確保ならびに土地使用料の一括払いの妥当性などが明言されており、それを知った人々は怒り心頭に発し、各地で激しい抗議活動を展開。その勢いは沖縄全土にまで広がり、ついには琉球政府首脳陣が総辞職決意の表明を行うまでにいたりました。
こうして一括払い・新規接収への反対運動は、沖縄全域に広がる「島ぐるみ闘争」へと発展していったのです。

那覇市の国映館前に掲げられたプライス勧告に反対する横断幕(沖縄県公文書館所蔵)。
島ぐるみ闘争(反対運動の激化)
1956年6月20日、プライス勧告の全文が発表されると、全64市町村のうち56もの市町村で住民大会が開かれるなど、反対運動はその規模を急激に拡大させていきました。老若男女、主義思想を超えて全住民が一致団結したこの運動は「島ぐるみ闘争」と呼ばれ、日本本土に暮らすウチナーンチュ(沖縄出身者)からの支援も多く寄せられました。
とりわけ、7月28日に那覇高校で行われた「四原則貫徹県民総決起大会」には、総勢約15万もの住民が参加。長年、米軍の理不尽な抑圧に耐えてきた住民の怒りがピークに達した、まさにその瞬間でした。

四原則貫徹をテーマに行われた住民大会の様子(沖縄県公文書館所蔵)。
こうした抗議運動の活発化を受けて、米国民政府は米軍人や軍属の民間地域への立入りを禁ずる「オフリミッツ」を発令。これには、地元住民とのトラブルを避けるという名目がありましたが、実際には、基地に依存する地域経済へダメージを与えるのが目的でした。また、学生が反米的だとして、琉球大学への財政援助の打切りおよび学生の処分もあわせて要求。その結果、6名の生徒が除籍処分となりました。
さらに翌年の1957年初頭、米国民政府のレムニッツァー民政長官は琉球政府の行政主席や立法院議長らと会談し、一括払いならびに土地の新規接収はアメリカの最終方針であると発表。同年2月には「米合衆国土地収用令(布令164号)」を公布し、その実施に取り掛かりました。
布令では、米軍がすでに取得していた「賃借権」の代わりに「限定付き土地保有権」という権利が設定され、地主の所有権は建前上残されるものの、実際には(土地使用料の一括払いと引き換えに)土地所有権が永久に拘束されることになるため、これは事実上の買上げともいえました。
また、こうして足場固めを行った米国民政府は、1957年5月、那覇空港や嘉手納飛行場をはじめ、読谷村・勝連村・恩納村など14市町村にわたる軍用地に対して、次々と限定付き土地保有権による収用を宣告。住民の意向を顧みず地代の一括払いを強要するアメリカ側の姿勢に、島ぐるみ闘争はますます激しさを増していきました。
土地闘争の終結と新土地政策
なかなか解決の糸口が見つからない軍用地問題に、ようやくひとつの転機が訪れたのは1958年4月のことでした。立法院本会議において、米国民政府のモーア高等弁務官が「土地接収計画については、現在ワシントンにて再検討されている」というメッセージを発表。同時に「軍用地料の一括払いを中止する旨の指令があった」ことも明らかになり、人々は、近い将来、この問題に関して何かしら大きな進展があるのではと期待しました。
このような情勢のなか、時の立法院では、当時の行政主席である當間重剛氏をはじめとする使節団のワシントン派遣を決定。米国側からの正式招待もあり無事アメリカに渡った一行は、沖縄の民意を反映させるため折衝に尽力しました。その結果「沖縄の軍用地問題については、現地の高等弁務官と沖縄側との折衝で解決すべき」との共同声明が発表され、現地米軍と沖縄側との直接折衝によって解決策を見出していくことになったのです。

ワシントンで折衝の席につく代表使節団の當間重剛行政主席(沖縄県公文書館所蔵)。

使節団がアメリカ本国から沖縄に戻った際の様子(沖縄県公文書館所蔵)。
この共同声明を受け、同年8月には、さっそく米琉双方からなる現地折衝会議がスタート。軍用地料の一括払い廃止を含むさまざまな懸案事項について討議が行われた結果、11月3日の最終会談において「原則的に双方の意見が一致した」との共同声明が発表されました。さらに翌月12月18日には、米国民政府のブース高等弁務官によって正式に「新土地政策」が発表され、次々と新たな布令や民立法が制定されていきました。
まず1959年1月には、「土地賃借安定法」および「アメリカ合衆国が賃借する土地の借賃の前払いに関する立法」が制定され、さらに同年2月には「賃借権の取得(布令20号)」が公布。軍用地料の毎年払いをはじめ、軍用地の取得や地代の評価など、制度面についての確立が図られていきました。
こうして長期にわたって繰り広げられてきた「島ぐるみ闘争」は一応の終結をみたわけですが、実際には、依然として多くの不平等が残されていました。しかしながら、そうした課題を差し引いても、戦後の土地問題に大きな進展をもたらしたという意味において、この合意はひとつのターニングポイントであったと言えるでしょう。
拡大する土地の新規接収
前項で述べたとおり、米国民政府による新土地政策の発表によって、軍用地問題はひとまずの終息を迎えました。
しかしながら、新規の土地収用については引き続き容認されていたことから、米軍はその後も断続的に基地を拡張・新設。共産圏諸国との緊張が高まり、インドシナ半島への軍事介入が顕著になった1960年頃には、相次いで関連工事や用地接収が行われるようになりました。

機能強化のために工事が行われた嘉手納飛行場の様子(沖縄県公文書館所蔵)。
また、ベトナムへの派兵が本格化すると、帰還兵や休暇兵による事故や事件が急激に増加。米軍人・軍属による犯罪件数も年間1000件を超え、その多くが未検挙のまま処理されたため、住民の感情は一気にヒートアップ。これまでの土地を対象とした抗議活動から、より全体的な反米・反戦運動へと変化していきました。

1965年6月、小学5年生の女子生徒が米軍のトレーラーの下敷きとなった現場(沖縄県公文書館所蔵)。
こうした流れのなか、1970年にはコザ市(現:沖縄市)で地元住民が米軍車両数十台を焼き払う事件、いわゆる「コザ暴動」が発生。このことは、1972年に予定されている本土復帰を前に、沖縄にはまだまだ解決しなければならない問題が山積していることをあらためて示すものとなりました。
次回ブログへと続きます。
…ということで、1950年代後半以降の土地闘争の歴史を振り返ってみましたが、いかがでしたでしょうか。少々、カタい内容になってしまったように思いますが、今回ばかりはご容赦いただけますと幸いです。
戦後の混乱のなか、自らの土地を取り戻すためにどれだけ多くの苦労があったか。今では当たり前とされている「毎年払いの軍用地料(賃借料)」を勝ちとるまでに、人々がどれほど辛酸をなめてきたのか。そんなことを今回の記事を通して、少しでも知っていただけましたら本望です。また、これから軍用地を購入される方は、ぜひそうした先人たちの歴史を頭の片隅に置いておいていただけると幸いです。
次回ですが、本土復帰以降の基地返還の流れや今後の返還計画など、軍用地の将来的なことについて話をしていければと思います。
それではまた、次回のブログをお楽しみに!
参考文献)
- 沖縄の米軍基地 平成30年12月(沖縄県)
- 一般社団法人沖縄県軍用地等地主会連合会ホームページ
- 土がある明日がある(桑江朝幸/沖縄タイムス社)